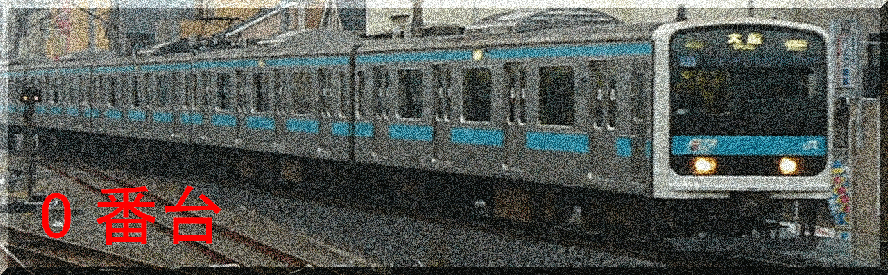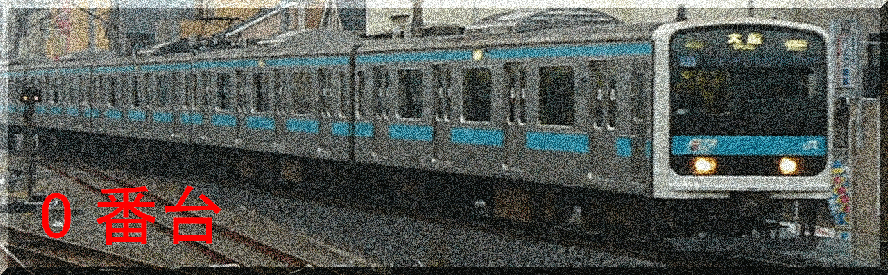What's mean serice 209?
〜209系とは?209系基礎知識〜
1993年から2005年まで製造されたJR東日本の低コスト新系列電車。
京浜東北線には1992年登場の試作車やその後の転属車を含め830両が走っています。
現在、京浜東北・根岸線以外でも中央・総武緩行線、八高・川越線(八王子〜高麗川〜川越)、
常磐線各駅停車〜地下鉄千代田線直通で活躍しているほか、
常磐線快速・普通電車(上野〜取手〜水戸・勝田方面)には交直流電車ながら、姿形がそっくり似ているE501系、
また東京りんかい高速鉄道りんかい線(埼京線直通)には設計がほとんど同じの70-000系が
活躍しています。
また、京浜東北・根岸線以外は1つの番台に統一れています。
ここから、書く番台ごとの解説を始めます。
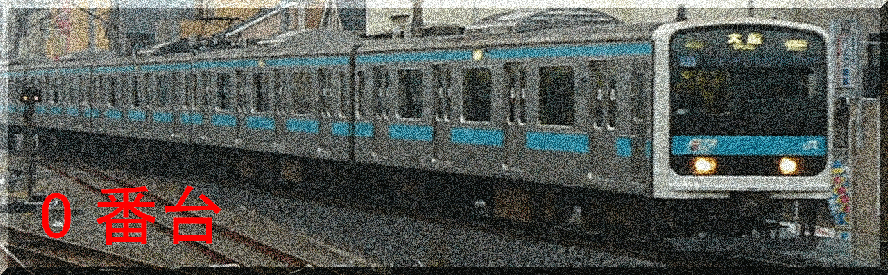
1993年に京浜東北・根岸線の103系を置き換える目的で登場し、1998年まで製造された。
現在、浦和電車区に10両編成78本(780両)と中原電車区に6両編成2本(12両)の
合計792両が配置され、京浜東北線・根岸線、南武線で走っている。
MT比は京浜東北・根岸線が4M6T、南武線は4M2Tである。
京浜東北線・根岸線用は登場当初は全車が4ドアであったが、
1995年(平成7年)度からは6扉車を連結した編成が登場、これまで未連結だった編成にも順次6扉車が組み込まれた。
車内の座席は折り畳み式で、平日の初電から9時30分までは座席を使用することができない(故障時を除く)。
現在、側面の窓を開閉出来るようにする改造工事が下十条運転区(東十条駅隣接)において行われている。
これは2005年、大森〜蒲田間で209系が工事用バケットに衝突したために京浜東北線が長時間運休となった際に、
喚起が不可能に近いことから体調不良を訴える者が続出したことが影響している。

6扉車 (蕨〜西川口にて)

改造された窓 (南浦和にて)

中央・総武緩行線の103系を置き換えるため、1998年(平成10年)11月に登場した。
中央・総武緩行線ではE231系の投入が予定されていたが、
当時主力だった103系に車両故障が頻発したため、急遽投入された。
170両(10両編成17本)が習志野区に新製配置され、その後はE231系によって同線の103系を置き換えた。
車体は従来車より150mm広くなった2,950mmの幅広車体が特徴。
また、0番台までは長い座席はすべて7人掛けだったが、
運転室直後の座席はのみ6人掛けとなっていることも特徴のひとつだ。
さらに行先表示器と運行番号表示機ををLED化した。
なお、中央・総武緩行線線にはE231系も走っているが主な相違点は以下の通りである。
・ 209-500は前面FRPが白なのに対し、E231では銀色になっている。
・ 209-500は6ドア車がないが、E231には6ドア車がある。
これまで習志野電車区(当時)に配置されていたが、2000年、京浜東北線のD-ATC化改造に伴う予備車確保と
輸送力増強用として2編成が習志野電車区から浦和電車区に転属した(代替として習志野電車区にE231系を投入)。
2005年10月には、窓改造による予備編成不足に対しそれを補うのためミツ515編成が浦和電車区に貸し出された(2006年3月に返却)。
しかし、京浜東北・根岸線の209系をE233系で置き換えることが決まり、
その前段階として500番台3本で試作車を置き換えることになった。
この対象はミツ513〜515となった。ミツ515はすでに決まっていたのか返却時は黄色の帯が太かった。
2006年12月12日現在、ミツ515が転属し、ミツ514も転属の為の改造工事を受けている。
現在、三鷹電車区に10両編成14本(140両)、浦和電車区に10両編成3本(30両)が配置されている。
今後も浦和電車区に2編成20両が転属する(前述)。


中央・総武緩行線 水道橋にて 京浜東北・根岸線 西川口にて
現在、ここまで完成。この先製作中です。
申し訳ございません!